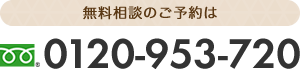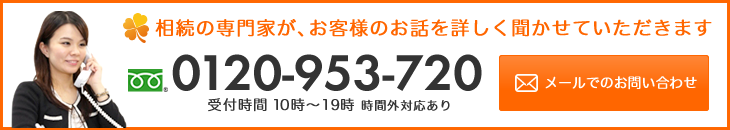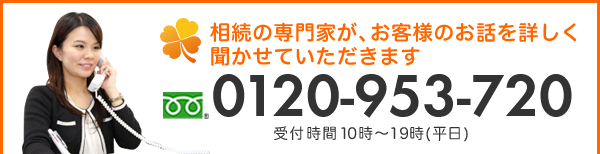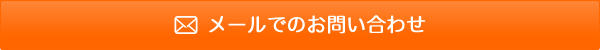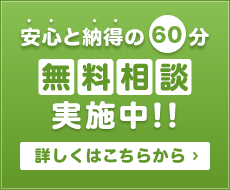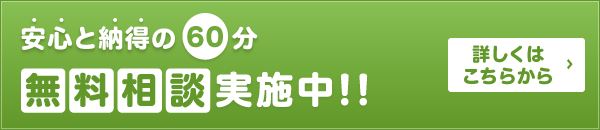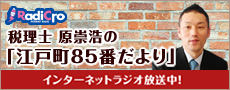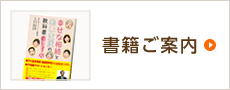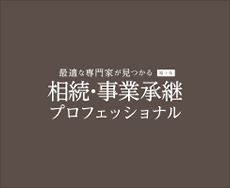2011.9.11 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、一言で言えば、相続人の代表者のことです。
どんなことをする人なのかと言えば、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。
■遺言執行者の職務
- 財産目録の作成
- 預貯金をおろす、株式を売る
- 遺言通りに財産をわける
- 遺言通りに不動産の売却や移転登記をする
- 認知の届出をする
- 相続人廃除、廃除の取り消しの申し立てを行う
※5、6の場合は必ず遺言執行者を決める必要があります。
遺言執行者の職務は多岐にわたり、上記はほんの一例です。
そのため、遺言執行の内容が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。
また、遺言執行者は未成年者と破産者を除いて、誰でもなることができます。
遺言執行者の指定は必ず遺言書でしなければなりません。
生前に口頭で遺言者と取り決めをしていたとしても、それは無効になります。
遺言執行者の指定は必ずしなければならないというわけではありませんが、
できれば指定しておいたほうが、その後の相続手続きがスムーズに進むことが
多いです。
2011.9.11 遺留分について
遺留分
遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の権利のことをいいます。
たとえば、長年連れ添った妻やまだ未成年の子供がいるにもかかわらず、遺言書で「全財産を○○(第三者)にあげる」としていたら、残された妻や
子供は生活に困ってしまいます。
そのため、民法では「遺留分」という権利が定められています。
遺留分の権利があるのは配偶者、直系卑属、直系尊属で、兄弟姉妹及びその代襲相続人は遺留分の権利はありません。
したがって、兄弟姉妹またはその代襲相続人だけが法定相続人の場合には、遺言書を書くにあたって遺留分に配慮する必要はありません。
相続人が兄弟姉妹だけという場合には、被相続人は全財産を赤の他人に贈ることもできます。
遺言者は遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を書く必要があります。
なお、遺留分が侵害されているからといって、その遺言書が無効となるわけではありません。
遺留分は放棄することができます。
遺言者の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分減殺請求権
遺留分権利者は、自分の遺留分を減らされた場合に、侵害された分を限度に
遺贈や贈与の効力を失わせることが可能です。
これを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求は、相続の開始と自分の遺留分を減らす遺贈または贈与があったことを知ってから1年で時効によって消滅します。
そのため、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うのが安全といえます。
また、自分の遺留分が侵害されていても、遺留分減殺請求をしないで遺言の内容を尊重しようと考える相続人もいますので、遺留分を侵害している
遺言書が必ずしも不適当というわけではありません。
2011.9.11 遺言書と遺書との違い
■遺言書
- 定められた形式にのっとっており、法的効力がある
- 自分の死後に配偶者や子供が困らないようお金を残したり、
世話になったひとに財産を寄付することができる - 死後に自分の愛情を周りに伝えられる積極的なメッセージとなる
また、
- 法律で定められた様式に従って作成しなければ効力が生じない
- 「公的文書」としての性格がある
- 財産や身分上の相続手続きの根拠書類になる
■遺書
- プライベートなメッセージを伝えられる。法的効力なし
また、
- 形式が決まっておらず、自由に書ける
- きわめて私的な文書で、他人に見せる必要がない
付言事項
遺言書には付言事項というものがあります。
これは遺言書の追記として、自分の気持ちを遺族に伝えるものです。
今まで伝えられなかった家族に対する感謝の想いや、なぜこの遺言書を書いたのか、このように遺産を分割した理由などを記載しておくと、遺族も納得しやすいでしょう。
付言事項は必ず書かなければならないというものではありません。