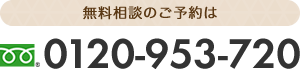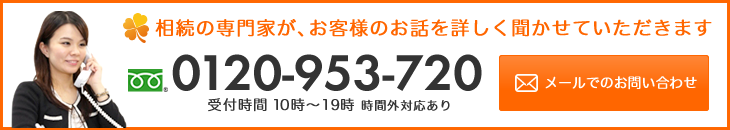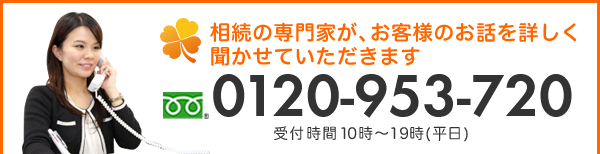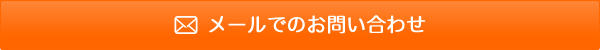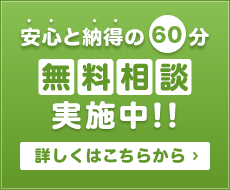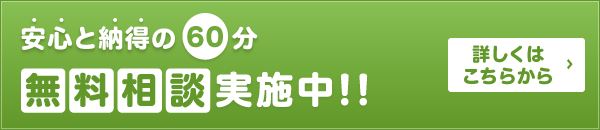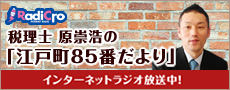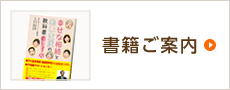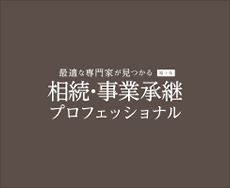2010.1.20 相続人と遺留分について
遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産をもらえる権利があります。
このように最低限もらえる遺産の一定部分を「遺留分」といいます。
被相続人は、生前贈与や遺言により財産を自由に処分することが出来ますが、この遺留分により財産の処分が制限されることとなります。
遺留分の権利者は
遺留分の権利があるのは次の相続人です。
- 配偶者
- 子・孫及びその世襲者
- 父母・祖父母等の直系尊属
相続財産に対する各相続人の遺留分
| (相続人が) 配偶者のみ | 2分の1 | |
| (相続人が) 配偶者と子 | 配偶者 | 4分の1 |
| 子 | 4分の1 (配偶者が死亡している場合は子が2分の1) | |
| (相続人が) 配偶者と父母 | 配偶者 | 3分の1 |
| 父母 | 6分の1 (配偶者が死亡している場合は父母が3分の1) | |
| (相続人が) 配偶者と祖父母 | 配偶者 | 2分の1 |
| 祖父母 | 遺留分なし | |
遺留分減殺請求とは
遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求権を行使して、自分のもらうべき遺産を返すように求めることができます。
この権利を行使するかどうかは相続人の自由となります。
夫がすべての財産(2000万円)を愛人に遺贈した場合、相続人が妻だけだとすると、妻は、遺留分の減殺請求権を行使して、遺産の1/2に相当する金額(1000万円)を愛人に請求することができます。
遺留分を考慮
遺留分は相続人が最低限もらえる遺産の一定部分です。
その遺留分を侵害した遺言書を作成すると、遺留分の減殺請求が行われ、紛争になる可能性があります。
残された遺族が遺産をめぐり争わないためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成が必要です。
2010.1.20 【2025年版】相続による不動産の名義変更|手続き・費用・注意点まとめ
2024年4月の法改正により、不動産の相続登記は義務化されました。
これにより、相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更を行わなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
相続による不動産名義変更は「義務化」されています
2024年4月の法改正により、不動産の相続登記は義務化されました。
これにより、相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更を行わなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
不動産の名義変更が必要なケースとは?
以下のようなケースでは、相続による不動産の名義変更が必要です。
- 宅地や建物を相続したとき
- 遺言書により不動産を取得したとき
- 遺産分割協議で不動産を引き継ぐとき
名義変更を放置すると、以下のような不都合が発生します:
- 売却や住宅ローンなどの担保設定ができない
- 相続人が増え、合意が困難に
- 書類の保存期間が過ぎ、必要書類の取得が難しくなる
不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れ
相続人の調査と確定(戸籍をさかのぼって確認)
遺産分割協議または遺言の確認
必要書類の収集
登記申請書と相続関係説明図の作成
法務局へ登記申請
※申請から登記完了までは、書類に不備がなければ1週間程度が目安です。
相続による不動産名義変更の3つのケースと必要書類
① 法定相続分での不動産名義変更
 相続人全員が法定相続分に従って不動産を登記するケースです。協議不要でスムーズに進められることが多いです。
相続人全員が法定相続分に従って不動産を登記するケースです。協議不要でスムーズに進められることが多いです。
必要書類
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍・改製原戸籍
- 住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図(作成)
② 遺産分割協議による名義変更
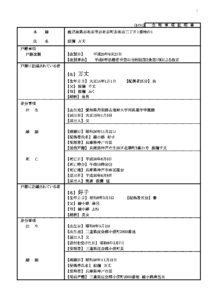 相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するか決めたうえで行う手続きです。
相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するか決めたうえで行う手続きです。
必要書類
- 上記と同様の戸籍・住民票類
- 固定資産評価証明書
- 印鑑証明書(相続人全員分)
- 遺産分割協議書(作成)
- 相続関係説明図(作成)
③ 遺言書による不動産名義変更
有効な遺言書がある場合、その内容に従って登記を行います。
必要書類
- 戸籍関係の書類一式
- 遺言書(公正証書・自筆など)
- 不動産を取得する相続人の戸籍・住民票
- 固定資産評価証明書
- 印鑑証明書(必要に応じて)
- 相続関係説明図(作成)
不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用
| 費用項目 | 概算金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産評価額 × 0.4% |
| 書類取得費 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬 | 5万円〜10万円前後 |
※物件の数や相続内容により変動します。
土地を分けて相続する場合は「分筆登記」が必要
相続人が1つの土地を共有せず分割したい場合、土地分筆登記という手続きが必要になります。
この場合、まず土地を分けたうえで、各人ごとに相続登記を行います。
専門家に依頼するメリット
相続登記は自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで以下のような利点があります。
- 書類の不備や申請ミスを防げる
- 法務局とのやりとりを任せられる
- 相続人間のトラブルを防止しやすい
- 節税対策や二次相続を見越したアドバイスが可能
よくある質問(FAQ)
Q:不動産の名義変更は自分でできますか?
A:可能ですが、専門知識や細かな書類作成が必要なため、司法書士などに依頼するのが一般的です。
Q:相続放棄した人も関係ありますか?
A:放棄の有無を確認するための書類や手続きが必要な場合があります。
Q:相続による不動産の名義変更はいつまで?
A:原則、相続を知った日から3年以内です(2024年施行の義務化より)。
相続登記でお困りの方は、まずは無料相談を
不動産の名義変更は「一生に数回あるかどうか」の大切な手続きです。
当センターでは、行政書士・司法書士・税理士が連携し、スムーズかつ確実なサポートを行っています。
▶【相続登記の無料相談・お見積りはこちら】
お気軽にご相談ください。
2010.1.20 寄与分
相続の公平性を保つために、
相続人の中に、被相続人に対し特別な働きをした者がいれば、その相続人の相続分には寄与分が加算されます。
寄与が認められるケースとして、
- 被相続人の事業を手伝っていた
- 被相続人の事業に資金を提供し、それにより事業が発展した
- 病気の被相続人の世話をして、看護費用が節約できた
が該当しますが、寄与分は算定が難しく、争いのもとになりがちです。
家庭裁判所の遺産分割調停では、寄与分がよく主張されますが、一般的には、寄与分を取り下げて調停が成立する場合が多いのが現状です。