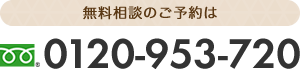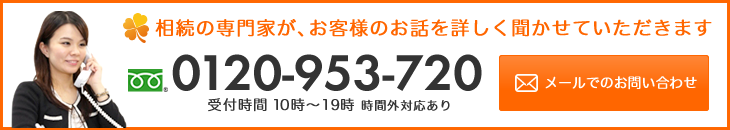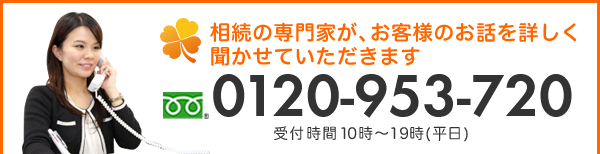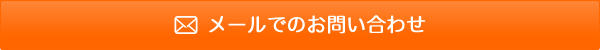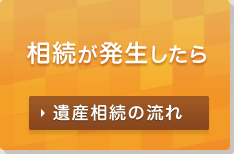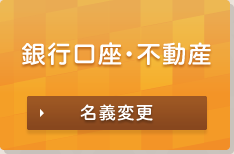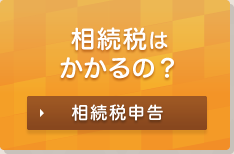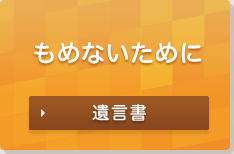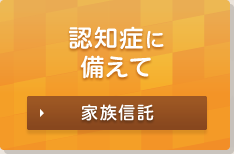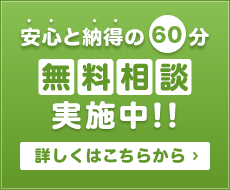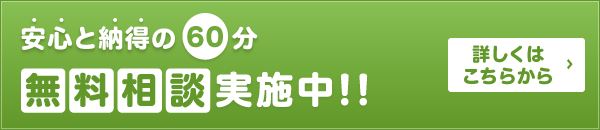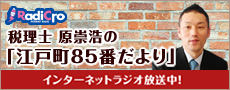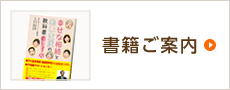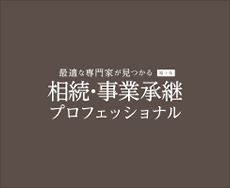江戸町85番だより第53回(2021年4月放送分)
原:今日はですね、保険の話をしようかなと思います。ジャッキーさん結構お詳しいかと思いますけども。
ジャッキー:そうですね。保険が一応専業ではありますからね。
原:ジャッキーさん色んなことしすぎて何専業かよー分からなくなってますけども。保険ですね。税金と保険って何が関係あるのかと言いますと、
ジャッキー:普通の人は分からないでしょうね。
原:そうですね、保険って、死んじゃったら、事故が起こった時にお金もらえるやつでしょってイメージだと思いますけども、
ジャッキー:税金に何が関係すんのって 原:実はあの保険って使い方によって節税になりますよね。知ってる人はですね、こういう会社の社長さんとかも含め節税商品とかっていうのは聞くかと思います。保険を払うことで節税になるっていうイメージがなかなかつきにくいかと思いますので、簡単にお話しさせていただこうかなと思います。会社さんで生命保険を掛けます。商品的にはまあ普通です。お金を掛けて事故、死亡事故とか保険事故とかが起こった時にお金が入ってくる。仕組み自体はですね、変わらないんですけども、その保険料を払うことで、それが経費になります。経費になるということはその分税金が減額、節税になることになりますね。税金減ります。で、お金払うだけでしたら、節税というか全然得じゃないんですけど、
ジャッキー:経費払ったということだけですもんね。接待、交際で飲食したでも経費は経費ですよね。
原:そうですね。何でも一緒だと思っちゃいますけども。実は保険の種類によってはお金が返ってくるものがあります。名前にすると解約返戻金というものですね。自分で保険料を払って経費にしていきますけれども、最終的にですね解約返戻金が返ってくると。
ジャッキー:解約をすると解約返戻金としてお金が返ってくる、会社に戻ってくるというものがあると
原:結局その自分が払ったものが返ってくるということなんで払って経費にしつつ最終的にはもう一回お金を返してもらえるという。そこだけ聞くとすごいお得みたいな感じがします。
ジャッキー:お得ですよね、そういう意味でええのないんかみたいなのは社長さんによく言われますね。
原:得するやつないんかみたいなね。まさに言葉だけ取るとすごいですよね。払って経費になってそのままお金に返ってくる。すごいと思うんですけど、保険が節税になるという意味での商品、はご理解いただけると思うんですけど、これって実はお金を返してもらったときにちゃんと課税されるんですよね。まあどれくらい課税されるかは保険の商品によるんですけど。基本的に払ったときに経費になるってものは返してもらったときにも今度逆に売り上げになるというか。なので本当の仕組みとしてはそんな得するものじゃないっていうか、今まで経費にしてきた合計分を最後お金もらって、返してもらったらそのまま課税の対象になるというのが実際の仕組みかなと思います。
ジャッキー:払っていた時はまあ経費で、お金払ってるその分節税なりました。ということですけど、じゃあいざ解約しました、お金返ってきました。ゆうたらそれは、利益や売り上げみたいな感じですよね。そこにはそのまま課税される。ようは繰り延べただけみたいな、そんなイメージですね。
原:払いだしてから、一番最後解約するときまでの期間を複数年で考えると、実は全然お得にはなってないが、節税にはなってないんですけど、1年1年払い続けている間はちゃんと経費になっていって、かつ貯金できているという仕組みなので、その間だけ見ると節税できていると。
ジャッキー:入り口はそうですね。
原:ていうのは商品になっています。
ジャッキー:あれ逆に何年も払ってきてていざ一気に解約したら何年もたまっていたやつが一気に返ってくるから逆に損じゃないかと思うんですけどどうなんですか。
原:まさにその通りです。損とは言いませんけど、わかりやすく毎年100ずつ経費にするとしますね、100100100って経費にしてて10年たったら1000の経費になってますね、10年たった時にそれを解約すると、ほぼ逆に100×10年1000の解約が発生します。
ジャッキー:返ってくるとしたら1000返ってくるんですね。累進課税構造で累進はあっちに乗っかったら税率高いんちゃうのって思うんですけど
原:まさにそうです。そうかんがえると損ですね。
ジャッキー:普通に払ってきてた方が税金少なかったんとちゃうのって。まあ結果的にそういうこともありえますよね。
原:さすがするどいですね。実はこの節税商品の最後の仕上げがありまして、最後返ってくるときに、いろいろ大きなお金を使いましょうねって。そこで課税されないように、そのときによくあるのが退職金をがばっと出すとか、大きく修繕するとか。とにかくいっぺんにお金がいるようなことを経費にできるよう当てて、最初返ってきたものが課税されないようにしましょうっていうのが、保険節税商品の仕組みになっていますね。
ジャッキー:出口がすごく大事だということですね。
原:さすが専門家(笑)みなさんね、入るときにええのんないのって入ってますけど終わりのところ、を考えたところで節税の契約をされるのがいいですね。入口のことだけを考えると後でなんもなかったていうことになりますね。
ジャッキー:100%返ってきての話ですけど、保険で100%返ってくるってほぼないですかね。
原:ではこのあたりはみなさんだいたい保険で節税っていうのはわかっていただいたかと思うんですけど、今日はちょっとジャッキーさんに教えていただこうかなと思います。
ジャッキー:質問ですか、専門の先生に。
原:いっつも鋭い答えをジャッキーさんにいただくので、今日もびっしっと。
ジャッキー:びっしっといけるかな(笑)
原:社長さんでしたらよく思う素朴な疑問ですけど、保険って色々あると思うんですけど、今言った節税をしようと思うにあったって、何でもいいんですかね。保険屋さんが話してくれる商品って。
ジャッキー:いや、何でもいいわけではないですね。これは保険税務、保険や税金の扱いがありますから、平成30年までのルールとそれ以降でコロッと変わったので、平成30年前までで変わったものといえば、医療保険や定期保険とか保険の種類で分類されてて、これは経費というか全額経費でいいですよとか。このルールだったらいいですよとか、そういうルールがあったんですよね。それが今解約返戻金の返礼率で何割まで落していいですよみたいなルールに今変わってます。もうなんかだいぶ難しくなってます。結局何でもいいわけではなくて今は解約返戻率の高いものは落とせる割合が、経費にできる割合が、保険料の何割っていうのが小さくなる。
原:そしたら、節税っていうことでたくさん経費にしたいけど最終たくさん返ってきてくれないともったいないじゃない、減ってますよね。でたくさん返ってくるものは経費にできる割合が少ないということですね。
ジャッキー:いまそういうルールに変わりました。
原:私も知らないふりして知ってるという、仕事でね(笑)あんまりこう活用しにくくなってますよね、節税だ
ジャッキー:毎年毎年の効果だけで言うと、解約返礼率、ようは沢山戻ってくるやつのが落とせる割合、経費にできる割合が減ったので支払いごとの効果っていうのが今までよりは、こんだけしか落とせないのかみたいなのはあると思うんですけど。
原:複雑ですね
ジャッキー:ものすごい今回複雑なので、途中から全部っ経費にしていいよっていう期間があって。期間ででてきたり。途中は、これ全額として、そのあと取り崩して、もうわけのわからんルールになっています。
原:今の話も知らない人は多分わかりにくい、そう思いますけど。
ジャッキー:ようは入口効果薄いけど、その切り替わるタイミングとかがあって、その最終的に先ほど先生がおしゃった出口にこんだけお金を残したいんだということを目標にしてどのくらい効果があるかっていう計算をすれば、ものすごくメリットは出るんですよ。こう、今迄みたいに全部落とせるからいいよねみたいな話はないってことです。
原:そしたらそのバランス的にお金が払って経費になる割合と、できるだけたくさん返ってくる割合と、いいところってあるんですか
ジャッキー:商品によって全部、あの保険会社がいろんな商品の作り方をしてるので、解約返戻金のタイミングとか、ピークの年数とか、それぞれ違うので、いつがいいですよみたいなのってやっぱり難しいですね。一個一個やっていかないと。
原:そっれってじゃあ商品自体もう、まあ無数にあるじゃないですか。じゃあこの何が一番いいってどうやって探したらいいんでしょう。
ジャッキー:もうあの社長様の年齢とか、まず年齢によって保険料とか、返礼の率が変わってきたりとかする。まずそのご自身の年齢からいつくらいにお金をたくさん使う、物を作りたいみたいな。この時間経過を置いたら、それをピンポイントに商品をあてがっていく方が。それはもうたくさん商品を扱っている人に聞いた方がいいですよね。
原:なんかええのんないのみたいな、言われてましたけど、なんかええって言われても、じゃあどう使いたいですかっていう意味をまず持ってくださいって言いう感じですかね
ジャッキー:そうですね、入り口で経費作って節税したいというニーズだけでは、たぶん保険商品を選ぶのはリスク高いなって思いますね。
原:とっても複雑ですよね、
ジャッキー:もうすごくわかりにくくなりましたね。説明するのもわかりにくいいう感じです。
原:もうほぼ、オーダーメイドに近い
ジャッキー:そうですね、そもそもオーダーメイドだったと思うんですけど、よりたぶん複雑になったぶんよりピンポイントにしないとこうしたいなと思っているところには到達しないんだろうなって。
原:あの保険会社にもいろいろあると思うんですけど、どこでもいいんですか。
ジャッキー:どこでもいいと思いますよ。別にここが好きここがきらいもあるでしょうし、まあ僕保険会社の商品がここがいいとか悪いとかあんまないと思うんですよ。そもそも保険契約っていうのはある程度契約保護されているので、たとえば破綻したとしても契約が0なるか言われたら、そうはならないですし、ある程度保護されていますから。
原:ある程度?
ジャッキー:ちゃんと契約ごとに保護されてますから(笑)一定のルールがあって、それごとに基づいて保護されてるので、それ大丈夫なんですけど、あとは好みもあると思いますので、外資系嫌いやとか日本のが信用できひんよねとか、それにこだわらなければ全部の会社のなかから選べばいいという一番ベストな。
原:さっきその条件っていうかベストなのってできるだけ沢山経費になってできるだけ沢山返ってきてっていうのが自分の年齢と目的に応じて一番いいやつ、ってなんかすごい針の孔通すような、そんな感じですよね。それってだれか見つけてくれるんですか。その営業マンとか、
ジャッキー:まあ出会う人でしょうね。まあそりゃ見つけてくれる人もいると思います。
原:それってじゃあ世にある保険会社の製品をある程度知っててこの人はこれがいいんじゃないかっていう風にして見積もってもらうっていうみたいな?えーすごいですね。保険の人って
ジャッキー:まあみんながどこまでやっているかは知りませんけど。(笑)僕らだったらいわれたことを忠実にピンポイントに探す、いろんな商品並べて、こういうことですよねって見てもらって選んでもらうようにはする。まあ会社によって返戻金の動きは違うのでピンポイントであればここだし、こっちの会社だったらピンポイントの期間が長いんですよね、でも高いんですよ。ピークの時間が長い方がよければこっちです、とか。2.3年前後見てくださいよならそうするし、両方見てもらったらなんとなくわかるんちゃいますかね。
原:すごいです。それだけでも結構ね、どっか一つの会社だけでなく色々見てやったらそれすごいですね。
ジャッキー:そうですね、でもそういう風にしてほしいですよね。
原:保険って高い買い物ですもんね。
ジャッキー:自分やったらそうしてほしいなって思うので。
原:こういう保険の商品や社長さんってどういう人に向いてるって、向いてないとかありますか。保険節税。
ジャッキー:今年儲かって、来年どうなるかわからんねんみたいなやつは絶対向いてないと思います。
原:逆にあるあるですよね。今年だけ特需で儲かったからどうにかしてくれへんって(笑)
ジャッキー:それはもう保険使わんほうがいいです、ちょっと裏技的なのあるんですけど。ちょっと危険かなって思うので。
原:やっぱり今年だけと思って高額なのは言っても払い続けるという支払い余力がいるんですね。
ジャッキー:結局払っていってこその効果が出てくる商品になってるんで。
原:そうなるととりあえずこれでみたいな。結構大きな買い物で
ジャッキー:そういった保険って結構高い。返戻金が多くたまるやつってもともとの保険料が結構高い商品が多いので。やっぱそれなりの金額になりますよね。
原:税理士的に見てて、なかなか経費でいっぺんに何百万が経費になる支払いってないんですけど、この保険って実はいけるんですよね。何割とかはありますけど、500万経費になるということができるんでなかなか普通にもの買って何億も経費にすることはできないので、そういう意味では決算直前にお金払ってどかっと利益減らす
ジャッキー:金額が高くとれるっていうので保険に群がって、外交員のほうもそういう商品をよく販売してたと思うんですけど、
原:逆に今返礼率もあんまりになってきているとそういう売り方ができなくなってきてるんですかね
ジャッキー:そうですね、今年だけとか短期間だけ返礼率を経費にして、っていうやり方はできないかな、向いていないかなと思いますね
原:そこそこの期間をお金を持ち続けれるひとはこの節税なかなかいけるっていうことですかね。
ジャッキー:そうですね、長期で見てどこかで大きな出費を作っていく。先ほど退職金っておっしゃられてましたけど、そういう出口に向けて徐々にためていくっていう意味で言えば、節税効果を得ながら出口で課税されないっていう方法での効果はあります。
原:なるほど、さすが専門家ジャッキーさん
ジャッキー:まあ専業ですのでね(笑)
原:今日の話とっても良かったです。いっぺんに経費になれるっていうのではなく、後先のことも考えるっていうのですね。
おわり