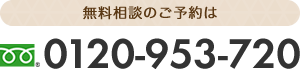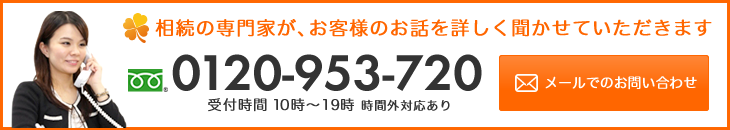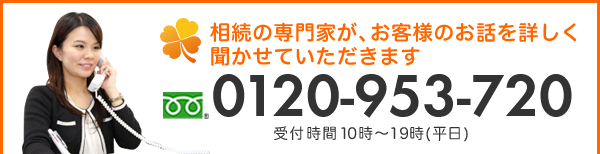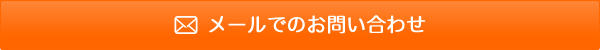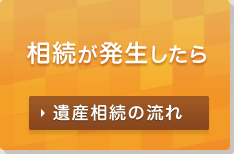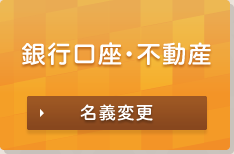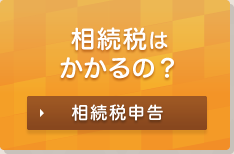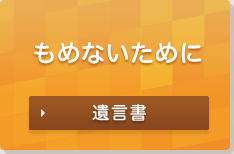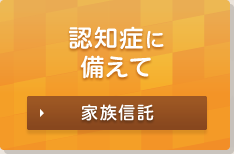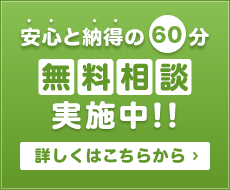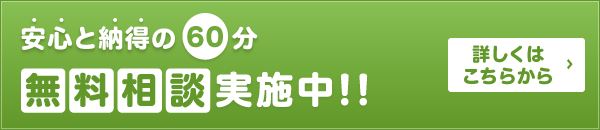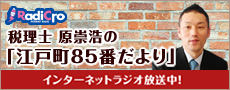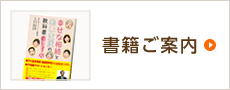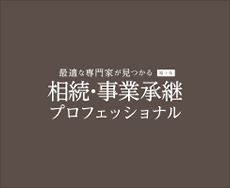相談Q&A


相続が発生したらまず何をしたらよいのですか。
相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかの確認をしてください。
その次に、相続人を公的な書類によって確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍収集を行います。
戸籍収集と同時並行で財産調査を行います。
戸籍収集と財産調査が完了したら、誰がどの財産を相続するかの話し合い(遺産分割協議)を行います。
手続きの詳細につきましては、当センターへお問い合わせください。
その次に、相続人を公的な書類によって確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍収集を行います。
戸籍収集と同時並行で財産調査を行います。
戸籍収集と財産調査が完了したら、誰がどの財産を相続するかの話し合い(遺産分割協議)を行います。
手続きの詳細につきましては、当センターへお問い合わせください。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを書く方がよいですか。
自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがあるので一概にどちらがいいとは言えません。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあればすぐに書くことができます。また費用もかかりません。しかし、法律的に不備な内容であったり、方式の不備で遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。
遺言発見者が自分に不利なことが書かれていたら破棄したり、隠匿や改ざんをしてしまう可能性もあります。
それに対して公正証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要がないので、その後の相続手続きを速やかに進めることができます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、破棄や隠匿、改ざんの心配もありませんので、安全確実な方法といえるでしょう。
ただ、公正証書遺言は費用がかかり、証人2人の立会いが必要となります。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあればすぐに書くことができます。また費用もかかりません。しかし、法律的に不備な内容であったり、方式の不備で遺言書が無効になる可能性があります。また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。
遺言発見者が自分に不利なことが書かれていたら破棄したり、隠匿や改ざんをしてしまう可能性もあります。
それに対して公正証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経る必要がないので、その後の相続手続きを速やかに進めることができます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、破棄や隠匿、改ざんの心配もありませんので、安全確実な方法といえるでしょう。
ただ、公正証書遺言は費用がかかり、証人2人の立会いが必要となります。
相続税の申告が必要かどうかわからないのですが
一度、当センターへお問い合わせください。
資料等を見ての判断が必要な場合も多いため、ご予約の上ご来所いただき、必要かどうかをご回答させていただきます。
資料等を見ての判断が必要な場合も多いため、ご予約の上ご来所いただき、必要かどうかをご回答させていただきます。
認知症になったら遺言書を作成することはできますか。
遺言書の作成に関しては『遺言をする時において、その能力を有しなければならない(民法963条)』と規定されています。
この能力とは、自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力のことを言い、「遺言能力」または「意思能力」と言われています。
遺言能力・意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、遺言条項及びその理解力等によって総合的に判断されることになります。したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけではありません。
しかし、認知症の可能性があった方の遺言書については、この遺言能力について相続人間で争われることもあります。
なお、成年被後見人が有効に遺言をするためには、医師2人以上の立会いが必要とされています。
この能力とは、自分の行う遺言が法律的にどのような効果を生じるかを理解する能力のことを言い、「遺言能力」または「意思能力」と言われています。
遺言能力・意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、遺言条項及びその理解力等によって総合的に判断されることになります。したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけではありません。
しかし、認知症の可能性があった方の遺言書については、この遺言能力について相続人間で争われることもあります。
なお、成年被後見人が有効に遺言をするためには、医師2人以上の立会いが必要とされています。
相続に関して、弁護士・司法書士・行政書士・税理士等誰に何を相談したらよいのですか。
相続はそう何度も経験することではないので、慣れない法的手続きをまとめて行うには大変な時間と労力がかかります。
そのため、専門家の力を借りることをお勧めいたします。
そのため、専門家の力を借りることをお勧めいたします。
弁護士…相続に関する紛争解決サポート(調停・裁判における代理権を有す)
司法書士…相続登記(土地・建物)の名義変更、裁判所への申立書類の作成
税理士…相続に関する税務サポート、相続税の申告代行
行政書士…一連の相続手続きサポート、相続人を確定させるための戸籍収集、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成
神戸相続サポートセンターでは、『相続ワンストップサービス』をご提供しております。
税理士事務所が母体ですので相続税の申告代行はもちろんのこと、司法書士と連携し、相続手続きから相続登記まで当事務所が窓口となって対応致します。
相続税を少なくする分割の方法を教えてください。
相続税を少なくする分割の方法の一部をご紹介致します。
- 被相続人に配偶者と子供がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合で、相続財産がそれほど多くなく、二次相続時(一次相続をした配偶者の死亡時)に税負担が生じない場合では、配偶者の税額軽減を使えるように財産を分割するのが有利となってきます。
二次相続時に相続税が発生する場合には、一次相続時で配偶者の取得分を多くして配偶者の税額軽減を使うと、二次相続での子供の負担が予想以上に重くなることがありますのでご留意ください。
配偶者と子供との分割では二次相続も考慮し、税額のシミュレーションをした上での分割が望ましいのではないでしょうか。 - 高収益物件がある場合
賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、一次相続で配偶者が取得すると二次相続時の財産が増えてしまうので、子供が相続することが望ましいでしょう。その他土地や株式など、将来値上がりが期待される財産も一次相続で子供が相続するのがよいでしょう。 - 土地の取得方法の工夫
相続財産のなかで、土地を複数の相続人で分割して取得した場合には、分割後の利用区分ごとの評価となるため、相続税が安くなることがあります。
当センターは税理士事務所が母体ですので、相続税の概算の算出や、最適な分割方法のアドバイスも致します。
詳細につきましては無料相談をご利用ください。
相続させたくない人がいるのですが。
生前でも、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行といった事由があれば、遺留分(相続財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人に法律上、必ず残しておかなければならないとされている一定割合額のこと)のある相続人の相続権を奪うことができます。
この制度を相続廃除といいます。これは、一方的に相続権を剥奪するという重大な行為なので、家庭裁判所に請求することによって可能となります。
下記のいずれの方法で行うことができます。
- 生前に家庭裁判所へ請求
- 遺言に廃除することを記載の上、遺言執行者が家庭裁判所に請求
また、排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求でき、遺言によって取り消すことも可能です。
長男が住宅を購入するというので資金援助をしたいのですが。
父母や祖父母など直系尊属から自己の居住用の住宅の取得のための資金援助の贈与を受けた場合には、一定額までは贈与税が課税されないという特例があります。
この特例を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、相続時精算課税の特例や贈与税の基礎控除と併用することができますので、かなり有利な規定となっています。
詳細につきましては、無料相談をご利用ください。
この特例を受けるには一定の要件を満たさなければなりませんが、相続時精算課税の特例や贈与税の基礎控除と併用することができますので、かなり有利な規定となっています。
詳細につきましては、無料相談をご利用ください。
故人の預金は勝手に使っていいのですか
正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となりますので、勝手に使うことはできません。
しかし、死亡後金融機関で故人の口座が凍結されるまでに、葬儀費用等でお金を引き出すことは多々見受けられます(望ましいことではありませんが・・)。
このような場合には、後日問題とならないように相続人間での了解を得ておくことが賢明です。
また、これらについては、遺産分割できっちりと精算をすることが必要です。
しかし、死亡後金融機関で故人の口座が凍結されるまでに、葬儀費用等でお金を引き出すことは多々見受けられます(望ましいことではありませんが・・)。
このような場合には、後日問題とならないように相続人間での了解を得ておくことが賢明です。
また、これらについては、遺産分割できっちりと精算をすることが必要です。
土地や建物の名義は変えないといけないのですか
登記は任意ですので、変える必要はありません。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。
故人に認知していた子供がいたようなのですが
法律上婚姻関係の無い男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。
非嫡出子でも、生前(遺言でも可)に認知していれば、法定相続人となります。
認知していない(遺言もない)場合は、法定相続人に該当しませんので、遺産相続に関する権利は一切ありません。
非嫡出子でも、生前(遺言でも可)に認知していれば、法定相続人となります。
認知していない(遺言もない)場合は、法定相続人に該当しませんので、遺産相続に関する権利は一切ありません。
財産の分割がまとまらないのですが
「遺産分割」に期限はありません。
時には中立な第3者に入ってもらい、お互いが納得できるまでじっくり話し合いをされることが重要です。
「10か月以内に分割を」という話を聞かれたことがあるかと思いますが、こちらは「相続税の申告期限」のことです。
それまでに分割できていなければ「未分割」として、一旦法定相続分で申告・納付を行い、後日分割確定後清算することになります。
その場合、配偶者の税額軽減等各種特例が使えないため、本来よりも多くの納税資金が必要となることがありますので、相続税のかかる方は10か月以内に分割協議を終えることが望ましいと言えます。
「いくら話し合いをしても分割がまとまらない」ということになれば、家庭裁判所に申し出て、「調停」→「審判」という流れの中で分割が決定されることになります。
時には中立な第3者に入ってもらい、お互いが納得できるまでじっくり話し合いをされることが重要です。
「10か月以内に分割を」という話を聞かれたことがあるかと思いますが、こちらは「相続税の申告期限」のことです。
それまでに分割できていなければ「未分割」として、一旦法定相続分で申告・納付を行い、後日分割確定後清算することになります。
その場合、配偶者の税額軽減等各種特例が使えないため、本来よりも多くの納税資金が必要となることがありますので、相続税のかかる方は10か月以内に分割協議を終えることが望ましいと言えます。
「いくら話し合いをしても分割がまとまらない」ということになれば、家庭裁判所に申し出て、「調停」→「審判」という流れの中で分割が決定されることになります。
机の中から遺言書が出てきたのですが
遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し,「検認手続」を受けなければなりません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが
二つの方法が考えれます。
一つは、生死不明の状態になってから7年が経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てるということです。
これにより連絡の取れない相続人は「7年経過時点で亡くなっている」ことになり、その方の相続人(又は代襲相続人)が分割協議に加わることができるようになります。
二つ目は、「不在者のための財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人が不明者の代わりとなって分割協議を進めるという方法です(正式には「代わり」ではなく、「管理人」の名の通り分割決定後の財産管理者としての立場であり、分割協議の最終決定には家庭裁判所の許可が必要です)。
どちらを行うかは、相続人間で十分検討のうえお進めください。
一つは、生死不明の状態になってから7年が経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てるということです。
これにより連絡の取れない相続人は「7年経過時点で亡くなっている」ことになり、その方の相続人(又は代襲相続人)が分割協議に加わることができるようになります。
二つ目は、「不在者のための財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人が不明者の代わりとなって分割協議を進めるという方法です(正式には「代わり」ではなく、「管理人」の名の通り分割決定後の財産管理者としての立場であり、分割協議の最終決定には家庭裁判所の許可が必要です)。
どちらを行うかは、相続人間で十分検討のうえお進めください。
分ける財産が自宅しかないのですが
遺産分割でもめるパターンとして、「遺産に占める不動産の割合が多い」場合があげられます。
今回のように自宅しかない場合で、かつ、その自宅に相続人の一人が住んでいるといった場合は「心情的に」分割で悩むことになります。
まずは、住まれている方がその自宅を相続し、その方が他の相続人に対し、自分の金融資産の中から必要額を支払う(代償分割)という方法が考えられます。
もし、支払う金融資産の無い場合は、共有持分での相続となりますが、住んでいる方も不安でしょうし、他の相続人も自由にできない資産ということであまり好ましいことではありません。
このようなことにならないためにも事前の「相続対策」は重要なのです。
今回のように自宅しかない場合で、かつ、その自宅に相続人の一人が住んでいるといった場合は「心情的に」分割で悩むことになります。
まずは、住まれている方がその自宅を相続し、その方が他の相続人に対し、自分の金融資産の中から必要額を支払う(代償分割)という方法が考えられます。
もし、支払う金融資産の無い場合は、共有持分での相続となりますが、住んでいる方も不安でしょうし、他の相続人も自由にできない資産ということであまり好ましいことではありません。
このようなことにならないためにも事前の「相続対策」は重要なのです。